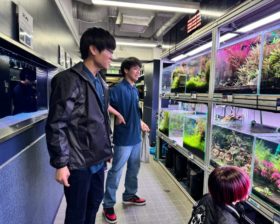2013年6月24日
淀川調査に行ってきました~水族館・アクアリスト専攻~
石田です。
先日、水族館・アクアリスト専攻1年の授業にて淀川の調査実習を行いました。
梅雨時なので、空模様が心配でしたが、小雨に降られたものの何とか実施できました。


淀川と言うと、コンクリート堤防で囲まれた汚い川をイメージされる人も多いと思いますが、JR大阪駅からわずか5kmの距離のところに写真のような自然がまだ残されているのです。
もちろん、以前は自然破壊されていたところでしたが、淀川両側の河川敷に「わんど」という池をつくり、自然を再生したところなのです。
しかし、歩いている足元をよく見ると、土の下にコンクリートブロックが見えたり、人工的な敷石の道があるなど、再生されたという痕跡がよくわかります。

それでも自然は確実に復活しつつあり、ここでは野生生物を見ることができます。カルガモの親子やアオサギなどの鳥がいて、さらには、ここには天然記念物であるイタセンパラという希少な魚も僅かに生息しています。

この絶滅危惧種のイタセンパラが、生き残っているかを確認することを目的に、毎年ここの調査実習を行ってきました。
今までの調査では、数は少ないながらイタセンパラの稚魚を発見しましたが、今年の調査では、例年発見した池には、イタセンパラを見つけることができず、他の多くの池を探し回って、最後に、かろうじてイタセンパラと思われる稚魚を発見できました。生息数の減少を改めて知ることができた今年の実習でした。

発見した稚魚は、生き残ってくれることを願いながらすぐに池に戻しました。
イタセンパラを守る看板が立てられ保護活動がなされていますが、残念ながら減少の一途をたどっています。

絶滅しかけている原因のひとつが、下の写真の魚です。この魚は、外来生物であるブラックバスの稚魚です。この魚が成魚になるとイタセンパラなどの在来種を皆食べてしまいます。

ブラックバスがこれほど多く繁殖していては、イタセンパラの将来が危惧されます。
この日は、淀川を管理されている専門調査員の方も来られて調査と駆除活動をされていまし


淀川には、ブラックバス以外にもミシシッピーアカミミガメ、ヌートリア、ブルーギル、タイリクバラタナゴなどの外来生物が多く居て、昔から生息していた在来生物にとって生息しにくい環境になっています。
いずれの外来種も人間が知らずに(知りながらの場合もある)持ち込んだのです。私達人間は、在来生物を守る責任があることを実習に参加した学生達が感じ取ってくれたらならば、今回の実習の目標を達成できたと思います。
あわせて読まれている記事
-

2024年9月11日
(おかやまフォレストパーク ドイツの森)に行ってきました【動物園・動物飼育専攻】
-

2024年8月19日
昆虫調査実習に行ってきました【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】
-

2024年6月8日
六甲山へ鳥類調査に行ってきました 【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】
-

2024年6月18日
1年生磯観察に行って来ました♪🐡 【水族館・アクアリスト専攻】
-

2024年11月2日
サバイバル実習に行ってきました【ECO自然環境クリエイター専攻】【野生動物&環境保護専攻】
-

2024年10月25日
【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】猛禽類調査実習へ行ってきました!
- 最近の投稿
- カテゴリ
- ECO’s Animal 10
- eco★news (1,826)
- SDGs 44
- アクア 195
- オープンキャンパス・体験入学 164
- ドッグスペシャリスト 2
- ドッグトレーナー 30
- ドルフィン 257
- ペット 154
- ペットトリマー 35
- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6
- ヤギメン 7
- 両生類 12
- 入学前授業 4
- 動物看護 10
- 卒後教育セミナー 8
- 卒業生の活躍 82
- 同窓会 10
- 哺乳類 55
- 啓蒙活動 4
- 在校生の活躍 147
- 大阪ECO水族館 40
- 学園祭 21
- 学校の動物紹介 134
- 学校の動物紹介 38
- 学校生活 332
- 学生広報チームcharm. 2
- 実習風景 515
- 就職 59
- 授業風景 210
- 未分類 125
- 未分類 728
- 校外イベント 292
- 校外実習 230
- 海外実学研修 135
- 爬虫類 42
- 特別講義 68
- 環境系 198
- 産学連携 72
- 緊急連絡 1
- 講師の先生 9
- 資格対策講座 6
- 飼育 1
- 飼育系 199
- 4年制 29
- アーカイブ
- 大阪ECOのブログ
- 最近の投稿
- カテゴリ
- ECO’s Animal 10
- eco★news (1,826)
- SDGs 44
- アクア 195
- オープンキャンパス・体験入学 164
- ドッグスペシャリスト 2
- ドッグトレーナー 30
- ドルフィン 257
- ペット 154
- ペットトリマー 35
- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6
- ヤギメン 7
- 両生類 12
- 入学前授業 4
- 動物看護 10
- 卒後教育セミナー 8
- 卒業生の活躍 82
- 同窓会 10
- 哺乳類 55
- 啓蒙活動 4
- 在校生の活躍 147
- 大阪ECO水族館 40
- 学園祭 21
- 学校の動物紹介 134
- 学校の動物紹介 38
- 学校生活 332
- 学生広報チームcharm. 2
- 実習風景 515
- 就職 59
- 授業風景 210
- 未分類 125
- 未分類 728
- 校外イベント 292
- 校外実習 230
- 海外実学研修 135
- 爬虫類 42
- 特別講義 68
- 環境系 198
- 産学連携 72
- 緊急連絡 1
- 講師の先生 9
- 資格対策講座 6
- 飼育 1
- 飼育系 199
- 4年制 29
- アーカイブ
- 大阪ECOのブログ